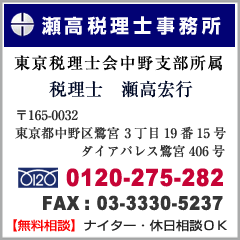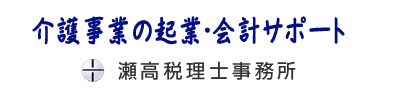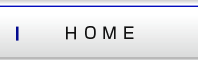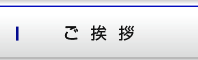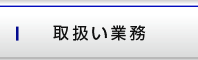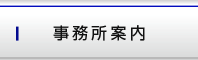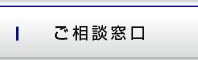- HOME
- 介護事業のサポート TOPページ
- 介護保険と支援費制度について
介護保険と支援費制度について
◆□◆ 介護保険とは ◆□◆
介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるように高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
ケアプラン作成事業者に相談すれば介護サービスを総合的に受けられます。
社会保険の仕組みにより、受けられる介護サービスと保険料との関係が分かりやすくなっています。
Ⅰ介護保険のあらまし
1.加入する方
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳から64歳までの方で医療保険の加入者
2. サービスが利用できる方
第1号被保険者については
・寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする方(要介護状態)
・常時介護は必要としないが、家事や身支度に支援を必要とする方(要支援状態)
第2号被保険者については
・ 初老期の痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態となった方
3. 保険料の支払方法
第1号被保険者については
・ 原則として老齢・退職年金からの天引きです
第2号被保険者については
・ 加入している医療保険の保険料に乗せして一括して納めます
4. 運営主体
制度の運営主体(保険者)は、市区町村です
5. 利用料の負担
介護保険のサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割が自己負担となります
Ⅱ サービスを利用するには
1.サービスを受けられる方
介護保険の介護保険サービスを受けられる人は次の方です。
・65歳以上の方
・40歳以上で介護保険が定める一定の疾病に該当する方
2.要介護認定について
上記に該当する方で介護サービスを利用したいと考えている方は、要介護認定の申請を行なって下さい。
介護保険の介護サービスを受けるためには、要介護認定を受けておく必要があります。
要介護認定とは、介護を受ける方がどの程度の介護を必要としているか認定するもので
「自立」「要支援1」「要支援2」」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の区分に認定されます。
この認定を受けて「要支援1」~「要介護5」に認定された方が、介護保険が適用されるサービス を受けることができます。
| ・自 立 | 介護保険のサービスは受けられません。 |
| ・要支援1 | 掃除など身の回りの世話の一部に手助けが必要。立ち上がり時などに、なんらかの支えを必要とする時がある。排泄や食事は、ほとんど自分でできる。 |
| ・要支援2 |
要介護1相当のうち、以下が該当しない人 1) 病気や怪我により、心身の状態が安定していない 2) 認知機能や思考・感情等の障害により、予防給付の利用に関わる適切な理解ができない 3) 心身の状態は安定しているが、予防給付の利用が困難な身体の状態 |
| ・要介護1 |
部分的介護を要する状態 立ち上がりや歩行などが不安定。入浴や排便に一部介助が必要 |
| ・要介護2 |
軽度の介護を要する状態 立ち上がりや歩行が一人ではできない。入浴や排便に一部または全面的介助が必要 |
| ・要介護3 |
中等度の介護を要する状態 入浴・排便・衣類着脱などに全面的介助が必要 |
| ・要介護4 |
重度の介護を要する状態 入浴・排便・衣類着脱のほか、日常生活に全面的介助が必要 |
| ・要介護5 |
最重度の介護を要する状態 生活全般にわたって全面的に介助が必要 |
|
※ 但し、福祉用具購入、住宅改修サービスは それぞれ上記限度額とは別枠で10万円及び20万 円が認められます。 |
|
2. 要介護認定方法について
要介護認定の流れ |
|
介護が必要な方(40歳以上の方) |
|
| ↓ | |
要介護認定の申請 |
|
| ↓ | |
役場保健福祉課介護保険係 |
|
| ↓ | ↓ |
市役所職員または |
主治医の意見書作成 |
| ↓ | |
介護支援専門員による訪問調査(聞き取り) |
|
| ↓ | |
結果をコンピュータに入力 |
|
| ↓ | |
コンピュータによる判定(一次判定) |
|
| ↓ | |
調査票の特記事項 |
|
| ↓ | |
主治医の意見書 |
|
| ↓ | |
介護認定審査会(二次判定) |
|
| ↓ | |
| 非 該 当 | 該 当 |
自立(介護保険のサービスは受けられません) |
要支援1、要支援2 |
≪主治医意見書≫
申請を受け付けた後、主治医に定期的に受診している以外は意見書作成のための診療を受けて下さい。
≪訪問調査≫
訪問調査員が申請者の自宅を訪れ、聞き取り調査を行なうものです。
日程については訪問調査員から前もって電話連絡があります。
訪問調査員は市町村職員または市町村から委託を受けた事業所の介護支援専門員です。
その後、市町村にて問調査員が作成した訪問調査票をコンピュータ判定で審査します。
そして介護認定審査会により、審査会委員がコンピュータ判定結果と主治医意見書を参考にしながら審査して、
判定(「自立」~「要介護5」)します。
≪介護認定審査会≫
福祉、医療保健分野の専門家が集まって、申請者がどの程度介護を必要としているかを審査、判定する会議です。
申請から認定結果が出るまでに約1ヶ月かかります。認定結果は郵送で通知されます。
要介護認定の結果、「要支援」~「要介護5」に認定された方は、この後ケアプランを作成することになります。
ケアプラン作成後、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と相談しながら、各サービス提供事業者を選択し、
サービス提供に関する契約を締結します。そして介護保険のサービス利用の開始となります。
≪その他≫
要介護認定の更新、再申請
新規認定は原則として6ヶ月の有効期間になります。また、更新認定については原則として12ヶ月の有効期間とし、
有効期間の終わりに近づいたら更新手続きを行なって下さい。更新手続きは有効期間終了日の60日前から行うことができます。
市町村から更新手続きの通知が届きます。また要介護認定を受けた後、身体の状態が大きく変わった場合は改めて申請することができます。
◆□◆ 支援費制度について ◆□◆
平成15年度に移行された支援費制度は、利用者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。 対象者は身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法により障害に該当する方で、住宅で利用できる居宅サービス(居宅生活支援)と、 施設に入所または通所して利用する施設サービス(施設訓練等支援)があります
▼ サービス内容(利用できるものに○印) ※障害児の施設サービスは措置制度です。
| 障害区分 | 身体障害者 | 知的障害者 | 障 害 児 | |
| 居 宅 サ | ビ ス |
サービス内容 | |||
居宅介護(ホームヘルプサービス) |
○ |
○ |
○ |
|
| 施 設 サ | ビ ス |
更正施設 |
○ |
○ |
|
申請からサービスまでの流れ
| 支 給 申 請 | |
| ↓ | サービス希望がある場合 市区町村に申請する。 |
| 支 給 決 定 | |
| ↓ | 市区町村は申請者の心身等の状況や介護状況を聞き取り、 |
| 事業者と契約 | |
| ↓ | 利用者は受給者証を、基に事業者とサービスに 関する契約をする。 |
| サービス提供 | |
| ↓ | 事業者は契約に基づく利用者にサービスを提供する。 |
| 負担額の支払い | |
| ↓ | 利用者は負担額を事業者に支払う。 |
介護事業の運営についてご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
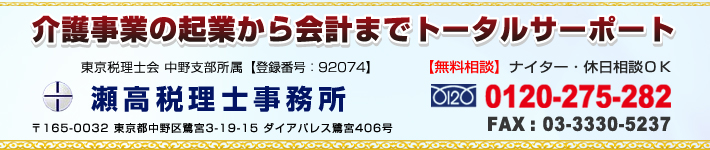
知っておきたい基礎知識