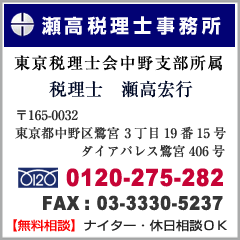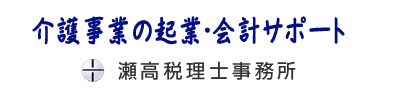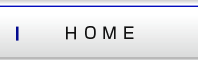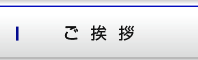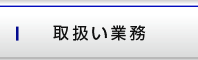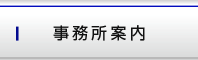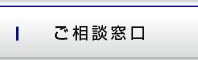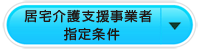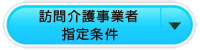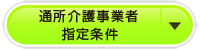- 俫俷俵俤
- 夘岇帠嬈偺僒億乕僩 俿俷俹儁乕僕
- 婲嬈僒億乕僩嬈柋偺撪梕
- 巜掕帠嬈幰偵側傞偨傔偵
- 捠強夘岇帠嬈幰偺巜掕忦審
巜掕捠強夘岇帠嬈幰乮僨僀僒乕價僗乯偵側傞偵偼
仧仩仧 巜掕忦審 仧仩仧
| 怑庬 | 恖堳婎弨 |
|---|---|
| 夘岇怑堳 |
夘岇怑堳偵偮偄偰丄師偺傾媦傃僀偺梫審 傾丗扨埵偛偲偵忢帪丄侾埲忋偺怑堳偑妋曐偝傟偰偄傞 僀丗棙梡幰偺悢偑侾俆恖傑偱偼侾埲忋丄侾俆恖傪挻偊傞応崌偼丄侾俆恖傪挻偊傞晹暘偺棙梡幰偺悢傪俆偱彍偟偰摼偨悢偵侾傪壛偊偨悢埲忋偺夘岇怑堳偑妋曐偝傟偰偄傞 掕堳10恖埲壓偱偁傟偽丄夘岇怑堳傑偨偼娕岇怑堳偑1埲忋昁梫 |
| 娕岇怑堳 |
娕岇怑堳偵偮偄偰丄扨埵偛偲偵娕岇怑堳傪侾埲忋攝抲丅 乮採嫙帪娫懷傪捠偠偰愱廬偡傞昁梫偼側偄偑丄採嫙帪娫懷傪捠偠偰摉奩捠強夘岇帠嬈強偲枾愙偐偮揔愗側楢実乮仸乯傪恾傞偙偲偑昁梫乯 乮仸乯搒偵偍偄偰偼丄乽枾愙偐偮揔愗側楢実乿偲偼丄暪愝傑偨偼嬤愙偵摨堦朄恖偺僋 儕僯僢僋傗巤愝摍偑偁傝丄僒乕價僗採嫙帪娫懷偵偍偄偰 僨僀偵嬑柋偟側偄応崌偼暪愝巤愝摍偱廬嬈偟偰偍傝丄僨僀偱懳墳偑昁梫偲側傟偽捈偪偵嬱偗偮偗傜傟傞忬嫷偱偁傞応崌偵丄暪愝巤愝摍偱偺寭柋壜偲偟偰巜掕偟偰偄傞丅 |
| 惗妶憡択堳 | 惗妶憡択堳偵偮偄偰丄採嫙傪峴偆帪娫悢偵墳偠偰丄侾埲忋偺怑堳偑妋曐偝傟偰偄傑偡偐丅 |
| 婡擻孭楙巜摫堳 | 帠嬈強婯柾偵學傜偢丄侾埲忋偺攝抲偑昁梫丅奺帠嬈強偵偍偄偰嶔掕偡傞捠強夘岇寁夋偵埵抲偯偗傜傟偨僒乕價僗撪梕偑揔愗偵採嫙偱偒傞攝抲偱偁傞偙偲丅 |
| 娗棟幰 |
娗棟幰偼丄尨懃偲偟偰忢嬑偐偮愱廬偑梫審偱偡丅 偨偩偟丄巟忈偑側偄応崌偵偼丄傾枖偼僀偵傛傝寭柋偑壜擻偱偡丅 傾丗摉奩捠強夘岇帠嬈強偵偍偗傞懠偺怑庬偺寭柋 僀丗摨堦晘抧撪偺暿帠嬈偵偍偗傞寭柋 |
俀丏愝旛婎弨
慡懱乹婎弨忋昁恵偺愝旛乺
仩 怘摪 仩 婡擻孭楙幒 仩 帠柋幒
仩 惷梴幒 仩 憡択幒 仩 僩僀儗丒庤愻偄
仩 悀朳乮怘帠傪挷棟偟偰採嫙偡傞応崌乯 仩 梺幒乮擖梺僒乕價僗傪採嫙偡 傞応崌乯
怘摪丒婡擻孭楙幒
偦傟偧傟昁梫側峀偝傪桳偟丄撪朄偵傛傝應掕偟侾恖偁偨傝俁噓亊棙梡掕堳埲忋偺柺愊傪妋曐偟偰偔偩偝偄丅 傑偨丄偦傟偧傟偵偍偄偰巟忈偑側偗傟偽摨堦偺応 強偲偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 嫹瑗側晹壆丒僗儁乕僗傪崌傢偣偰柺愊傪妋曐偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅
仴 柺愊偵嶲擖偱偒側偄晹暘
仢 懠愝旛乮惷梴幒傗帠柋幒丄尯娭晹暘丄捠楬丒楲壓晹暘丄悀朳丄帠柋僗儁乕僗摍乯
仢 懠帠嬈乮摉奩扨埵偲暿扨埵偺応崌傕娷傓乯偺怑堳摍偑怘摪媦傃婡擻孭楙幒撪傪捠傞峔憿偺応崌偺摉奩捠楬晹暘
仢 棙梡幰偑婡擻孭楙摍偵巊梡偱偒側偄晹暘乮椻憼屔傗扞摍僒乕價僗採嫙偺偨傔偵棙梡幰偑捈愙巊梡偟側偄廦婍摍偑偁傞応崌偼丄摉奩 僗儁乕僗偼柺愊偐傜彍偔乯
仢 摉奩寶暔偵偍偗傞捠楬丒楲壓晹暘偵偮偄偰偼丄尨懃偲偟偰怘摪寭婡擻孭楙幒偺柺愊偵嶼擖偱偒傑偣傫丅棙梡幰偑婡擻孭楙偺堦娐偲偟偰曕峴孭楙摍偵巊梡偡傞応崌傕摨條丅
仢 棙梡掕堳暘偺婘傗堉巕摍傪攝抲偡傞偙偲乮婘偼丄僒乕價僗採嫙撪梕偵傛傝柍偔偰傕壜乯
惷梴幒
惷梴幒偼丄屄幒枖偼僇乕僥儞摍偱巇愗傜傟偨宍忬偱偁傝丄惷梴偱偒傞愝旛偱偁傞偙偲
惷梴媥梴偑昁梫偵側偭偨棙梡幰偑揔帪媥傔傞傛偆丄摨堦僼儘傾偵偁傞側偳棙梡偟傗偡偄応強偵愝抲偡傞偙偲
怽惪帪偵偼丄儀僢僪偩偗偱側偔棙梡幰偑惷梴偱偒傞愝旛偲偟偰晍抍摍偺愝抲傕昁梫偱偡丅
憡択幒
棙梡幰媦傃偦偺壠懓偺僾儔僀僶僔乕妋曐偺偨傔丄屄幒枖偼僷乕僥乕僔儑儞摍偱巇愗傜傟偰奜晹偐傜偺帇慄傪幷抐偱偒傞宍忬丒偟偮傜偊偱偁傞偙偲
怽惪帪偵偼丄憡択傪庴偗晅偗傞偨傔偺愝旛乮婘丒偄偡摍乯偺愝抲偑昁梫偱偡丅
帠柋幒
摉奩帠嬈傪塣塩偡傞偨傔偺帠柋幒偑昁梫丅側偍丄怘摪婡擻孭楙幒撪偵帠柋偺偨傔偺僗儁乕僗傪暿搑妋曐偡傞応崌偵偼丄
摉奩僗儁乕僗偼怘摪婡擻孭楙幒偺柺愊偐傜偼彍奜偡傞偙偲
懠帠嬈乮夘岇曐尟奜帠嬈娷傓乯偲帠柋幒偑摨堦偺応崌丄捠強夘岇帠嬈愱梡偺帠柋婘侾埲忋妋曐偝傟偰偄傞偙偲
僩僀儗丒庤愻
梫夘岇幰偑埨慡偐偮塹惗揑偵巊梡偱偒傞傕偺偱偁傞偙偲
梺幒
乮擖梺夘彆傪峴偆応崌乯廫暘側扙堖僗儁乕僗傪愝偗傞側偳丄梫夘岇幰偑埨慡偐偮揔愗偵擖梺偟丄夘彆偱偒傞愝旛偱偁傞偙偲
僉僢僠儞
拫怘偺採嫙摍偱悀朳傪巊梡偡傞応崌丄悀朳傪愝抲偡傞偙偲
悀朳偼塹惗揑偵巊梡偱偒傞傕偺偱偁傞偙偲
悀朳丒僉僢僠儞偲偟偰廬嬈幰偑巊梡偡傞僗儁乕僗偼丄怘摪婡擻孭楙幒偺柺愊偵偼嶼擖偱偒側偄偙偲丅
側偍丄棙梡幰偑婡擻孭楙摍偺堦娐偲偟偰摉奩僉僢僠儞傪巊梡偡傞応崌偱偁偭偰傕摨條丅
挀幵応丒 憲寎僗儁乕僗
憲寎幵傪曐桳偡傞応崌偵偼丄揔愗側挀幵僗儁乕僗傪妋曐偡傞偙偲乮帠嬈強強嵼抧奜偱傕壜乯
憲寎僗儁乕僗偵偮偄偰偼丄摴楬岎捠朄傪弲庣偟丄岎捠丒墲棃偺朩偘偵側傜側偄傕偺偱偁傞偙偲丅
傑偨丄棙梡幰偑埨慡偵忔崀偱偒傞僗儁乕僗偱偁傞偙偲
屄恖忣曬曐娗偺偨傔偺愝旛
屄恖忣曬摍傪揔愗偵曐娗偡傞偨傔偺愝旛偲偟偰丄巤忶偱偒傞彂屔傪愝抲偡傞偙偲丅
亂 拲堄 亃
怽惪梊掕偺寶抸暔偵偮偄偰丄寶抸娭學朄椷丄徚杊娭楢朄椷摍懠朄椷偵偍偄偰丄巜掕捠強夘岇帠嬈傪峴偆偙偲偺偱偒傞寶暔丒抧堟偐偳偆偐丄帠慜偵妋擣偑昁梫偱偡丅
懠朄椷偵傛傝丄僨僀僒乕價僗帠嬈傪峴偆偙偲偑偱偒側偄偲敾抐偝傟傞応崌偵偮偄偰偼丄巜掕捠強夘岇帠嬈強偲偟偰巜掕偱偒傑偣傫丅
俁丏塣塩婎弨
僒乕價僗採嫙偺奐巒偵摉偨偭偰棙梡怽崬幰傑偨偼偦偺壠懓偵懳偟偰丄塣塩婯掕偺奣梫丄 夘岇怑堳摍偺嬑柋懱惂側偳偺廳梫帠崁傪婰偟偨暥彂傪岎晅偟偰愢柧傪峴偭偰棙梡怽崬幰偺摨堄傪摼傞偙偲偵側偭偰偄傑偡丅
仴 庡側崁栚偼師偺捠傝偱偡丅
1. 棙梡幰偵懳偡傞僒乕價僗偺愢柧偟丄摨堄傪摼傞
2. 惓摉側棟桼偑側偔僒乕價僗偺採嫙傪嫅斲偱偒側偄
3. 僒乕價僗採嫙崲擄帪偺懳墳
4. 梫夘岇擣掕摍偺怽惪偵學傞墖彆
5. 嫃戭僒乕價僗寁夋曄峏傪墖彆偡傞
6. 恎暘徹傪実峴偡傞
7. 僒乕價僗採嫙傪婰榐偡傞
8. 棙梡椏傪庴椞偡傞
9. 捠強夘岇寁夋傪嶌惉偡傞
10. 棙梡幰偺晄惓傪巗挰懞偵捠抦偡傞
11. 嬞媫帪偵偼庡帯堛偵楢棈側偳偺懳墳傪偡傞
12.塣塩婯掱傪掕傔傞
13.嬑柋懱惂偺妋曐摍
14.嫃戭夘岇巟墖帠嬈幰偵懳偡傞棙塿嫙梌偺嬛巭
15.嬯忣張棟
16.帠屘敪惗帪偺懳墳
係丏塣塩婯掕
亂 塣塩婯掕偺帠椺 亃 捠強夘岇 仜仜仜仜仜僒乕價僗僙儞僞乕塣塩婯掱偺椺
戞侾忦 乮帠嬈偺栚揑乯
姅幃夛幮仮仮偑奐愝偡傞仜仜仜仜仜僒乕價僗僙儞僞乕乮埲壓乽帠嬈強乿偲偄偆丅乯偑峴偆巜掕捠強夘岇媦傃巜掕夘岇梊杊捠強夘岇乮埲壓乽巜掕捠強夘岇摍乿偲偄偆丅乯
偺帠嬈乮埲壓乽帠嬈乿偲偄偆丅乯 偺揔惓側塣塩傪妋曐偡傞偨傔偵恖堳媦傃娗棟塣塩偵娭偡傞帠崁傪掕傔丄帠嬈強偛偲偵抲偔傋偒廬帠幰乮埲壓乽捠強夘岇廬帠幰乿偲偄偆丅乯偑丄
梫夘岇忬懺枖偼梫巟墖忬懺偵偁傞崅楊幰偵懳偟揔惓側巜掕捠強夘岇摍傪採嫙偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丅
戞俀忦 乮塣塩偺曽恓乯
侾丂帠嬈強偺捠強夘岇廬帠幰偼丄梫夘岇幰摍偺怱恎偺摿挜傪摜傑偊偰丄棙梡幰偑壜擻側尷傝偦偺嫃戭偵偍偄偰丄
偦偺桳偡傞擻椡偵墳偠帺棫偟偨擔忢惗妶傪塩傓偙偲偑偱偒傞傛偆丄偝傜偵棙梡幰偺幮夛揑屒棫姶偺夝徚媦傃怱恎婡擻偺堐帩暲傃偵壠懓偺恎懱揑丒惛恄揑晧扴偺寉尭傪恾傞偨傔偵丄
昁梫側擔忢惗妶忋偺悽榖偍傛傃婡擻孭楙摍偺夘岇丄偦偺懠昁梫側墖彆傪峴偆丅
俀丂帠嬈偺幚巤偵偁偨偭偰偼丄娭學嬫巗挰懞丄抧堟曪妵巟墖僙儞僞乕丄嬤椬偺懠偺曐寬丒堛椕枖偼暉巸僒乕價僗傪採嫙偡傞幰偲偺枾愙側楢実傪曐偪丄憤崌揑側僒乕價僗偺採嫙偵搘傔傞丅
戞俁忦 乮帠嬈強偺柤徧摍乯
帠嬈傪峴偆帠嬈強偺柤徧媦傃強嵼抧偼丄師偺偲偍傝偲偡傞丅
乮堦乯柤 徧 仜仜仜仜仜僒乕價僗僙儞僞乕
乮擇乯強嵼抧 廧強丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒
戞係忦 乮怑堳偺怑庬丄堳悢媦傃怑柋撪梕乯
帠嬈強偵嬑柋偡傞怑庬丄堳悢媦傃怑柋撪梕偼師偺偲偍傝偲偟丄奺怑堳偺堳悢偼暿巻偺偲偍傝偲偡傞丅
侾丂娗棟幰侾柤乮仜仜仜偲寭柋乯 娗棟幰偼丄帠嬈強偺廬嬈幰偺娗棟媦傃嬈柋偺娗棟傪堦尦揑偵峴偆丅
俀丂捠強夘岇廬帠幰
惗妶憡択堳仜柤 乮忢嬑 丂仜柤 仜仜仜寭柋 仜柤乯乮旕忢嬑丂仜柤丂 仜仜仜寭柋 仜柤乯
娕岇怑堳仜柤 乮忢嬑丂丂仜柤丂仜仜仜寭柋 仜柤乯乮旕忢嬑丂仜柤 仜仜仜寭柋 仜柤乯
夘岇怑堳仜柤 乮忢嬑 丂仜柤 仜仜仜寭柋丂仜柤乯乮旕忢嬑丂仜柤丂仜仜仜寭柋丂仜柤乯
捠強夘岇廬帠幰偼丄巜掕捠強夘岇摍偺嬈柋偵偁偨傞丅
惗妶憡択堳偼丄巜掕捠強夘岇摍偺棙梡怽崬偵偐偐傞挷惍丄捠強夘岇寁夋枖偼夘岇梊杊捠強夘岇寁夋乮埲壓乽捠強夘岇寁夋摍乿偲偄偆丅乯偺嶌惉摍傪峴偆丅
傑偨丄棙梡幰偵懳偟擔忢惗妶忋偺夘岇偦偺懠昁梫側嬈柋偺採嫙偵偁偨傞丅
夘岇怑堳丄娕岇怑堳偼棙梡幰偺怱恎偺忬嫷摍傪揑妋偵攃埇偟丄昁梫側擔忢惗妶忋偺夘岇傗寬峃娗棟丄偦偺懠昁梫側嬈柋偺採嫙偵偁偨傞丅
俁丂婡擻孭楙巜摫堳 仜柤乮仜仜仜偲寭柋乯
婡擻孭楙巜摫堳偼丄擔忢惗妶傪塩傓偺偵昁梫側婡擻偺尭戅傪杊巭偡傞偨傔偺孭楙巜摫丄彆尵傪峴偆丅
係丂娗棟塰梴巑仜柤 乮塰梴夵慞壛嶼傪偲傞応崌偼昁梫乯
娗棟塰梴巑偼棙梡幰偺塰梴 忬懺傪攃埇偟丄塰梴働傾寁夋偺嶌惉丄幚巤傪庡摫偟丄塰梴夵慞僒乕價僗偺採嫙傪峴偆丅
俆丂尵岅挳妎巑丒帟壢塹惗巑 仜柤
乮岥峯婡擻岦忋壛嶼傪偲傞応崌昁梫偩偑丄娕岇怑堳偱傕壛嶼偺嶼掕偼壜乯
岥峯婡擻偺忬懺傪攃埇偟丄岥峯婡擻夵慞娗棟巜摫寁夋偺嶌惉丄岥峯婡擻岦忋僒乕價 僗偺幚巤傪庡摫偡傞丅
俇丂挷棟堳 仜柤
乷仏埾戸偺応崌偼挷棟堳乮埾戸乯偲昞帵偡傞丅傑偨丄攝怘傪棙梡偡傞応崌偼婰嵹偟側偄乸 棙梡幰偺拫怘摍傪挷棟偡傞丅
俈丂塣揮庤 仜柤丂{仏埾戸偺応崌偼塣揮庤(埾戸)偲昞帵偡傞丅} 棙梡幰偺憲寎傪峴偆丅
俉丂帠柋怑堳摍仜柤丂帠柋怑堳摍偼丄捠強夘岇廬帠幰偺曗彆揑嬈柋媦傃昁梫側帠柋傪峴偆丅
戞俆忦 乮塩嬈擔媦傃塩嬈帪娫乯
帠嬈強偺塩嬈擔媦傃塩嬈帪娫偼丄師偺偲偍傝偲偡傞丅
乮堦乯塩嬈擔 仜梛擔偐傜仜梛擔 偨偩偟丄廽擔媦傃侾俀寧仜仜擔偐傜侾寧仜擔 傑偱傪彍偔丅
乮擇乯塩嬈帪娫 屵慜仜帪偐傜屵屻仜帪
戞俇忦 乮棙梡掕堳乯
帠嬈強偺棙梡幰偺掕堳偼丄壓婰偺偲偍傝偲偡傞丅
侾扨埵栚 僒乕價僗採嫙帪娫懷 屵慜仜帪偐傜屵屻仜帪 掕堳仜仜恖
俀扨埵栚 僒乕價僗採嫙帪娫懷 屵慜仜帪偐傜屵屻仜帪 掕堳仜仜恖
戞俈忦 乮巜掕捠強夘岇摍偺採嫙曽朄丄撪梕乯
巜掕捠強夘岇摍偺撪梕偼丄嫃戭僒乕價僗寁夋枖偼夘岇梊杊僒乕價僗寁夋乮埲壓乽嫃戭僒乕價僗寁夋摍乿摍乯偵婎偯偄偰僒乕價僗傪峴偆傕偺偲偡傞丅
偨偩偟丄嬞媫傪梫偡傞応崌偵偁偭偰偼丄嫃戭僒乕價僗寁夋摍偺嶌惉慜偱偁偭偰傕僒乕價僗傪棙梡偱偒傞傕偺偲偟丄師偵宖偘傞僒乕價僗偐傜棙梡幰偑慖掕偟偨僒乕價僗傪採嫙偡傞丅
侾丂恎懱夘岇偵娭偡傞偙偲 擔忢惗妶摦嶌擻椡偺掱搙偵傛傝丄昁梫側巟墖媦傃僒乕價僗傪採嫙偡傞
攔煏偺夘彆丄堏摦丒堏忔偺夘彆丄梴岇丄偦偺懠昁梫側恎懱偺夘岇
俀丂擖梺偵娭偡傞偙偲 壠掚偵偍偄偰擖梺偡傞偙偲偑崲擄側棙梡幰偵懳偟偰丄昁梫側擖梺僒乕價僗傪採嫙偡傞
堖椶拝扙偺夘岇丄恎懱偺惔怈丄惍敮丄愻恎丄偦偺懠昁梫側擖梺偺夘彆
俁丂怘帠偵娭偡傞偙偲 乷仏攝怘傪棙梡偡傞応崌偼丄怘帠偵娭偡傞偙偲乮攝怘乯偲婰嵹偡傞乸 媼怘傪婓朷偡傞棙梡幰偵懳偟偰丄昁梫側怘帠偺僒乕價僗傪採嫙偡傞
怘帠偺弨旛丄攝慥壓慥偺夘彆丄怘帠愛庢偺夘彆丄偦偺懠昁梫側怘帠偺夘彆乷仏攝怘傪棙梡偡傞応崌丄弨旛偼嶍彍乸
係丂婡擻孭楙偵娭偡傞偙偲 懱椡傗婡擻偺掅壓傪杊偖偨傔偵昁梫側孭楙媦傃擔忢惗妶偵昁梫側婎杮揑摦嶌傪妉摼偡傞偨傔偺孭楙傪峴偆
俆丂塰梴夵慞偵娭偡傞偙偲 掅塰梴忬懺偵偁傞棙梡幰摍偵懳偟偰丄塰梴怘帠憡択摍偺 塰梴夵慞僒乕價僗傪峴偆
俇丂岥峯働傾偵娭偡傞偙偲 岥峯婡擻偺岦忋傪栚揑偲偟丄岥峯惔憒丄愛怘丒殝壓婡擻偵娭偡傞巜摫庒偟偔偼僒乕價僗偺採嫙傪峴偆
俈丂傾僋僥傿價僥傿丒僒乕價僗偵娭偡傞偙偲 棙梡幰偑丄惗偒偑偄偺偁傞夣揔偱朙偐側擔忢惗妶傪憲傞偙偲偑偱偒傞傛偆丄傾僋僥傿價僥傿丒僒乕價僗傪幚巤偡傞丅
偙傟傜偺妶摦傪捠偠偰拠娫偯偔傝丄榁偄傗忈奞偺庴梕丄怱恎婡擻偺堐帩丒 岦忋丄帺怣偺夞暅傗忣弿埨掕傪恾傞丅丂椺乯儗僋儕僄乕僔儑儞丏壒妝妶摦丏惂嶌妶摦丏峴帠揑妶摦丏懱憖
俉丂憲寎偵娭偡傞偙偲 憲寎傪昁梫偲偡傞棙梡幰偵懳偟憲寎僒乕價僗傪採嫙偡傞丅憲寎幵椉偵偼捠強夘岇廬帠幰偑揧忔偟昁梫側夘岇傪峴偆
俋丂憡択丒彆尵偵娭偡傞偙偲 棙梡幰媦傃偦偺壠懓偺擔忢惗妶偵偍偗傞夘岇摍偵娭偡傞憡択偍傛傃彆尵傪峴偆
戞俉忦 乮巜掕嫃戭夘岇巟墖帠嬈幰偲偺楢実摍乯
侾丂巜掕捠強夘岇摍偺採嫙偵偁偨偭偰偼丄棙梡幰偵偐偐傞巜掕嫃戭夘岇巟墖帠 嬈幰枖偼巜掕夘岇梊杊巟墖帠嬈幰乮埲壓乽巜掕嫃戭夘岇巟墖帠嬈幰摍乿偲偄偆丅乯偑
奐嵜偡傞僒乕價僗扴摉幰夛媍摍傪捠偠偰丄棙梡幰偺怱恎偺忬嫷丄偦偺偍偐傟偰偄傞娐嫬丄懠偺曐寬丒堛椕丒暉巸僒乕價僗偺棙梡忬嫷摍偺攃埇偵搘傔傞丅
俀丂棙梡幰偺惗妶忬嫷偺曄壔丄僒乕價僗棙梡曽朄丒撪梕偺曄峏婓朷偑偁偭偨応崌丄 摉奩棙梡幰扴摉偺巜掕嫃戭夘岇巟墖帠嬈幰摍偵楢棈偡傞偲偲傕偵丄柸枾側楢 実偵搘傔傞丅
俁丂惓摉側棟桼側偔巜掕捠強夘岇摍偺採嫙傪嫅傑側偄丅偨偩偟丄捠忢偺帠嬈幚巤抧堟摍傪姩埬偟丄棙梡婓朷幰偵懳偟偰捠強夘岇枖偼
夘岇梊杊捠強夘岇乮埲壓乽捠強夘岇摍乿偲偄偆丅乯偺採嫙偑崲擄偲擣傔偨応崌丄摉奩棙梡幰偵偐偐傞巜掕嫃戭夘岇巟墖帠嬈幰摍偲楢実偟丄昁梫側慬抲傪島偢傞丅
戞俋忦 乮屄暿墖彆寁夋偺嶌惉摍乯
侾丂巜掕捠強夘岇摍偺採嫙傪奐巒偡傞嵺偵偼丄棙梡幰偺怱恎偺忬嫷丄婓朷媦傃偦偺偍偐傟偰偄傞忬嫷暲傃偵壠懓摍夘岇幰偺忬嫷傪廫暘攃埇偟丄墖彆寁夋傪嶌惉偡傞丅
傑偨丄偡偱偵嫃戭僒乕價 僗寁夋摍偑嶌惉偝傟偰偄傞応崌偼丄偦偺撪梕偵偦偭偨捠強夘岇寁夋傪嶌惉偡傞
俀丂捠強夘岇寁夋摍偺嶌惉丒曄峏偺嵺偵偼丄棙梡幰枖偼壠懓偵懳偟丄摉奩寁夋偺撪梕傪愢柧偟丄摨堄傪摼傞丅
俁丂棙梡幰偵懳偟丄捠強夘岇寁夋摍偵婎偯偄偰奺庬僒乕價僗傪採嫙偡傞偲偲傕偵丄宲懕揑側僒乕 價僗偺娗棟丄昡壙傪峴偆丅
戞侾侽忦 乮巜掕捠強夘岇摍偺採嫙婰榐偺婰嵹乯
捠強夘岇廬帠幰偼丄巜掕捠強夘岇摍傪採嫙偟偨嵺偵偼丄偦偺採嫙擔丒撪梕丄摉奩巜掕捠強夘岇摍偵偮偄偰丄夘岇曐尟朄戞 41 忦戞俇崁傑偨偼朄戞 53 忦戞俇崁偺婯掱偵傛傝丄
棙梡幰偵偐傢偭偰 巟暐偄傪庴偗傞曐尟媼晅偺妟丄偦偺懠昁梫側婰榐傪棙梡幰偑強帩偡傞僒乕價僗採嫙婰榐彂偵婰嵹偡傞丅
戞侾侾忦 乮巜掕捠強夘岇摍偺棙梡椏摍媦傃巟暐偄偺曽朄乯
侾丂巜掕捠強夘岇摍傪採嫙偟偨応崌偺棙梡椏偺妟偼丄暿巻椏嬥昞偵傛傞傕偺偲偟丄摉奩巜掕捠夘岇摍偑朄掕戙棟庴椞僒乕價僗偱偁傞帪偼丄偦偺妟偺侾妱偲偡傞丅
俀丂戞侾俀忦偺捠忢偺帠嬈幚巤抧堟傪墇偊偰峴偆憲寎偺岎捠旓丄巜掕捠強夘岇偵捠忢梫偡傞帪娫傪墇偊偰巜掕捠強夘岇傪採嫙偡傞応崌偺
棙梡椏丄怘嵽 椏旓丄偍傓偮戙丄傾僋僥傿價僥傿僒 乕價僗偵偐偐傞彅宱旓偵偮偄偰偼丄暿巻偵宖偘傞旓梡傪挜廂偡傞丅
俁丂戞侾崁媦傃戞俀崁偺旓梡偺巟暐偄傪庴偗傞応崌偵偼丄棙梡幰傑偨偼偦偺壠懓偵懳偟偰帠慜 偵暥彂偱愢柧偟偨忋偱丄巟暐偄偵娭偡傞摨堄傪摼傞丅
係丂巜掕捠強夘岇摍偺棙梡幰偼丄摉僙儞僞乕偺掕傔傞婜擔偵丄暿搑宊栺彂偱巜掕偡傞曽朄偵傛傝擺擖偡傞偙偲偲偡傞丅
戞侾俀忦 乮捠忢偺帠嬈偺幚巤抧堟乯
捠忢偺帠嬈偺幚巤抧堟偼丄仜仜嬫丄仜仜巗偲偡傞丅
戞侾俁忦 乮宊栺彂偺嶌惉乯
捠強夘岇摍偺採嫙傪奐巒偡傞偵偁偨偭偰丄杮婯掱偵増偭偨帠嬈撪梕偺徻嵶偵偮偄偰丄棙梡幰偵 宊栺彂偺彂柺傪傕偭偰愢柧偟丄
摨堄傪摼偨忋偱彁柤乮婰柤墴報乯傪庴偗傞偙偲偲偡傞丅
戞侾係忦 乮嬞媫帪摍偵偍偗傞懳墳曽朄乯
侾丂捠強夘岇廬帠幰摍偼丄巜掕捠強夘岇摍傪幚巤拞偵棙梡幰偺昦忬摍偵媫曄丄偦偺懠嬞媫帠懺偑惗偠偨偲偒偼丄
懍傗偐偵庡帯堛偵楢棈偡傞摍偺慬抲傪島偢傞偲偲傕偵丄娗棟幰偵曬崘偟側偗傟偽側傜側偄丅
俀丂巜掕捠強夘岇摍傪幚巤拞偵揤嵭偦偺懠偺嵭奞偑敪惗偟偨応崌丄棙梡幰偺旔擄摍偺慬抲傪島偢傞傎偐丄娗棟幰偵楢棈偺忋偦偺巜帵偵廬偆傕偺偲偡傞丅
戞侾俆忦 乮旕忢嵭奞懳嶔乯
帠嬈強偼丄旕忢嵭奞偵旛偊傞偨傔丄徚杊寁夋傪嶌惉偟旔擄孭楙摍傪師偺偲偍傝峴偆偲偲傕偵昁梫側愝旛傪旛偊傞丅
丒杊壩愑擟幰 娗棟幰丂丂丒杊嵭孭楙 擭仜夞丂丂丒旔擄孭楙 擭仜夞丂丂丒捠曬孭楙 擭仜夞
戞侾俇忦 乮塹惗娗棟媦傃廬帠幰摍偺寬峃娗棟摍乯
侾丂捠強夘岇摍偵巊梡偡傞旛昳摍偼惔寜偵曐帩偟丄掕婜揑側徚撆傪巤偡側偳偵塹惗娗棟偵廫暘棷堄偡傞傕偺偲偡傞丅
俀丂捠強夘岇廬帠幰偵懳偟姶愼徢摍偵娭偡傞婎慴抦幆偺廗摼偵搘傔傞偲偲傕偵丄擭侾夞埲忋偺寬峃恌抐傪庴恌偝偣傞傕偺偲偡傞丅
戞侾俈忦 乮僒乕價僗棙梡偵偁偨偭偰偺棷堄帠崁乯
棙梡幰偑擖梺幒媦傃婡擻孭楙幒摍傪棙梡偡傞応崌偼丄怑堳棫夛偄偺傕偲偱巊梡偡傞偙偲丅傑偨丄懱挷偑巚傢偟偔側偄棙梡幰偵偼偦偺巪傪愢柧偟埨慡巜摫傪恾傞丅
戞侾俉忦 乮憡択丒嬯忣懳墳乯
侾丂帠嬈強偼丄棙梡幰偐傜偺憡択丄嬯忣摍偵懳偡傞憢岥傪愝抲偟丄巜掕嫃戭僒乕價僗摍偵娭偡傞棙梡幰偺梫朷丄嬯忣摍偵懳偟丄恦懍偵懳墳偡傞丅
俀丂帠嬈強偼丄慜崁偺嬯忣偺撪梕摍偵偮偄偰婰榐偟丄偦偺姰寢偺擔偐傜俀擭娫曐懚偡傞丅
戞侾俋忦 乮帠屘張棟乯
侾丂帠嬈強偼丄僒乕價僗採嫙偵嵺偟丄棙梡幰偵帠屘偑敪惗偟偨応崌偵偼丄懍傗偐偵嬫巗挰懞丄夘岇巟墖愱栧堳丄棙梡幰偺壠懓摍偵楢棈傪峴偆偲偲傕偵丄昁梫側慬抲傪島偠傞丅
俀丂帠嬈強偼丄慜崁偺帠屘偺忬嫷媦傃帠屘偵嵺偟偰嵦偭偨張抲偵偮偄偰婰榐偟丄偦偺姰寢偺擔偐傜俀擭娫曐懚偡傞丅
俁丂帠嬈強偼丄棙梡幰偵攨彏偡傋偒帠屘偑敪惗偟偨応崌偵偼丄懝奞攨彏傪懍傗偐偵峴偆丅
戞俀侽忦 乮偦偺懠塣塩偵偮偄偰偺棷堄帠崁乯
侾丂廬帠幰偺幙揑岦忋傪恾傞偨傔丄尋廋偺婡夛傪師偺偲偍傝愝偗傞傕偺偲偟丄嬈柋懱惂傪惍旛偡傞丅
乮堦乯嵦梡帪尋廋 嵦梡屻俀偐寧埲撪
乮擇乯宲懕尋廋 擭俀夞埲忋
俀丂帠嬈幰偼丄嬈柋忋抦傝摼偨棙梡幰傑偨偼偦偺壠懓偺旈枾傪曐帩偡傞丅傑 偨丄廬帠幰偱偁偭偨幰偵丄嬈柋忋抦傝摼偨棙梡幰傑偨偼偦偺壠懓偺旈枾傪曐帩偡傞偨傔丄
廬帠幰偱側偔側偭偨 屻偵偍偄偰傕偙傟傜偺旈枾傪曐帩偡傞傋偒巪傪屬梡宊栺偺撪梕偵柧婰偡傞丅
俁丂帠嬈強偼丄偙偺帠嬈傪峴偆偨傔丄働乕僗婰榐丄棙梡寛掕挷彂丄棙梡幰晧 扴嬥挜廂曤丄偦偺懠昁梫側挔曤傪惍旛偡傞丅
係丂偙偺婯掱偺掕傔傞帠崁偺傎偐丄塣塩偵娭偡傞廳梫帠崁偼丄仏仏朄恖仮仮 偲仜仜仜僙儞僞乕 偺娗棟幰偲偺嫤媍偵婎偯偒掕傔傞傕偺偲偡傞丅
晬 懃
偙偺婯掱偼丄暯惉仜仜擭仜寧仜擔偐傜巤峴偡傞丅仸巜掕梊掕擭寧擔枖偼夵惓擭寧擔傪婰嵹
仚偙偺婯掱偺椺偼丄偁偔傑偱尰帪揰偱憐掕偝傟傞僀儊乕僕偱偁傝丄婰嵹偺巇曽傗偦偺撪梕偼丄婎弨傪枮偨偡尷傝丄擟堄偺傕偺偱峔傢側偄傕偺偱偁傞丅
夘岇帠嬈傪婲嬈偝傟傞曽丄偛憡択摍偛偞偄傑偟偨傜丄偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣壓偝偄丅
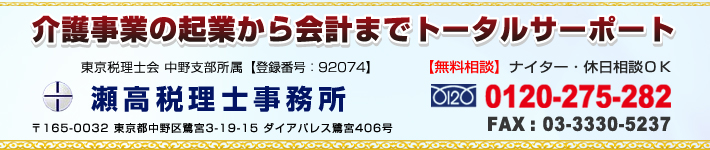
抦偭偰偍偒偨偄婎慴抦幆